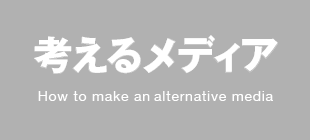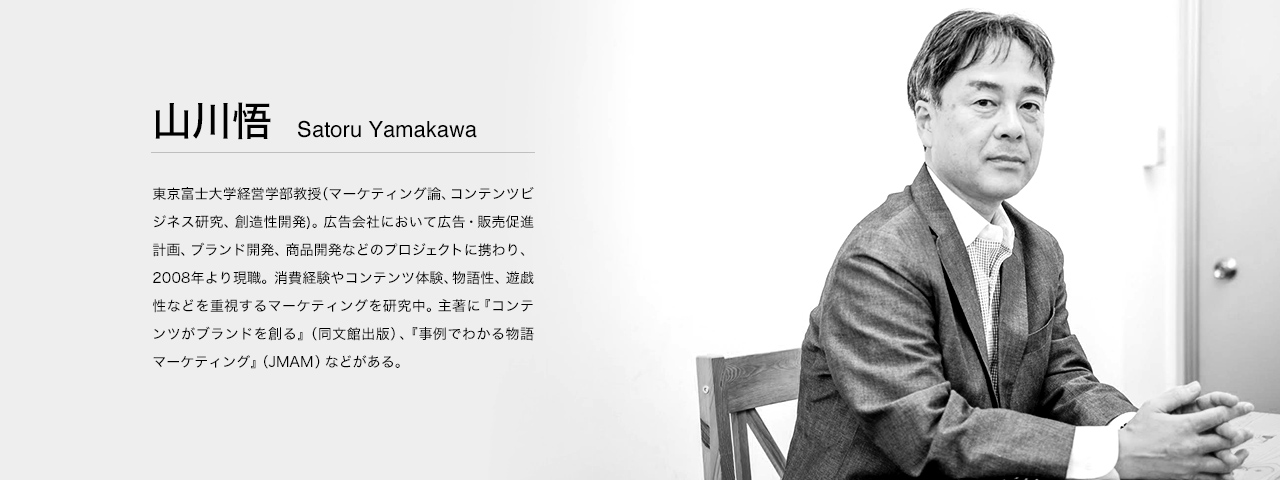感じさせられれば、ブランディングはうまくいく 〜新時代の五感ブランディング ①〜
2015.09.10
「五感ブランディング」という言葉を耳にする機会が増えてきました。簡単にモノが売れない時代のなか、旧来的な視覚中心のコミュニケーションだけではなく、視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚ーー五感を通じてブランドを伝える具体的な方法がいま、様々な企業で実践され成功を収めています。五感ブランディングの最先端を具体例とともに紹介していきます。
食品業界では「食感」が、繊維・アパレル産業では「素材の肌触り」が、トイレタリー分野では「香り」が、商品開発のメインテーマに位置しています
誰にでも「うまく理由は言えないけどお気に入り」という商品やお店があると思います。
スターバックスの珈琲の香りとBGM、ユニクロのインナー「エアリズム」の感触、ハーレーダビッドソンのエンジン音、ギネスビールのクリーミーな泡、三菱鉛筆「ジェットストリーム」の滑らかな書き味、ウェスティンホテルのホワイトティーの香り・・・。
これらは、私たちに「また使いたい」「また行きたい」と思わせるだけのブランド要素といえます。いい換えると「やみつき」を生み出す源泉なのです。
今日、食品業界では「食感」が、繊維・アパレル産業では「素材の肌触り」が、トイレタリー分野では「香り」が、商品開発のメインテーマに位置しています。テレビCMではもはや、視聴者の注目を獲得する「サウンドロゴ」が不可欠な要素になってきました。店舗やホテル、エアラインでも独自の香りで顧客を惹きつける工夫がなされています。
視覚以外の感覚要素でブランドを感じさせる「官能品質」の時代がやってきたのです。

スターバックスの珈琲の香りとBGM、ユニクロのインナー「エアリズム」の感触、ハーレーダビッドソンのエンジン音・・・「また使いたい」「また行きたい」と思わせるだけのブランド要素は「やみつき」を生み出す源泉となります
触覚・味覚・嗅覚・視覚・聴覚の五感を統合的に活用する
人間は普段、外界からの情報の8割を視覚から取っているといわれます。
かつてブランドとは、名称、ロゴタイプ、シンボルマーク、シンボルカラーなどの視覚的要素で表現されるものと考えられてきました。これらを統合して伝達する手法として、VI(ビジュアルアイデンティティ)の重要性が唱えられました。
しかし今日、ブランドらしさを伝える方法は、VIだけとは限らないというのが常識になりつつあります。視覚情報はたしかに、正確で多量の情報を伝えられますが、それだけでは弱い・残らない・物足らない、というのが現代の市場環境でもあります。視覚情報に他の感覚要素を組み合わせることで、顧客の心にブランドの記憶を深く刻むきっかけをつくりだす試みが注目されているのです。
このように触覚・味覚・嗅覚・視覚・聴覚の五感を統合的に活用し、強力なブランド構築を行なう手法を「五感ブランディング」と呼びます。もう10年くらい前から注目されてきた概念ですが、今日的な状況変化と事例を加味して、このテーマを考えてみましょう。
このブランドは「どんな香りであるべきか?」「テーマパークにしたら?」「カクテルにしたら?」ーー別の形式で接触・消費できるように考えてみるのです
多様な感覚でブランドに触れてもらおうとする試みも広まってきています。
東京・六本木に「メルセデス・ベンツ コネクション」が登場して以来、「フィアットカフェ」(港区)、「アウディ・カフェ・サイタブリア」(渋谷区)など、輸入車各社が続々とブランドカフェとでも呼ぶべき空間をオープンしはじめました。これらはブランド価値を、通常の商品・サービスとは異なる感覚器官で体験してもらおうという施設です。
ある感覚を表す言葉で別の感覚を示すことを「共感覚的比喩」と呼びます。例えば「暖かい色」は触覚表現が視覚に、「甘い歌声」は味覚表現が聴覚に用いられた例です。ブランドコミュニケーションにおいても、この共感覚的な戦略が有効になっているようです。
先に採り上げたのは「車をカフェにしたらどうなるか?」を具現化した例ですが、同様に、このブランドは「どんな香りであるべきか?」「擬人化したら?」「テーマパークにしたら?」「カクテルにしたら?」「テーマソングをつくったら?」など、別の形式で接触・消費できるように考えてみるのは有効な思考実験となるはずです。ブランドを商品の属性とみなすのではなく、ひとつの世界観と位置づけ、コト消費の対象にしていく考え方といえましょう。

車をカフェにしたらどうなるか? 「アウディ・カフェ・サイタブリア」はブランド価値を、通常の商品・サービスと異なる感覚器官で体験してもらおうという施設です
最近のトピックスとしては、商標法の改正を挙げることができます。
これまで特許庁に登録できる商標とは、文字・図形・記号といった形あるものに限られていました。しかし平成27年4月から、製品デザインやCMなどで使用される「音」「動き」「ホログラム」「位置」「色彩」などが商標登録できるようになりました。大幸薬品「正露丸」のラッパのメロディーなど、初日だけでも特許庁に170件を超える出願があったそうです。
しかし米国や豪州、欧州では、これら以外にも「香り」「触感」「味」「トレードドレス(商品の形状や包装、店舗の外観など)」が商標として認められています。久光製薬のサロンパスの香り(米国)、ベルベットの手触りのワインボトル(米国)、ダーツ用の矢に用いられる苦いビールの強い匂い(英国)、刈ったばかりの草の匂いがするテニスボール(EU)などです。ちなみにTPP交渉では、これらを日本でも認めさせようという動きもあるようです。
ただ日本の商業には本来、多様な感覚で顧客を楽しませようとする伝統があります。蒲焼のタレの香り、蕎麦をすする音、和菓子の色彩や触感、消費財としての薫香・・・。また江戸時代には楽曲を使った物売りが街中を賑わせ、一種の風物誌にもなりました。商標制度に捉われることなく、新たな五感マーケティングの手法が生まれてもよい土壌は、わが国には十分あるものと思います。

製品デザインやCMで使用される「音」「動き」「位置」「色彩」などが商標登録できるようになりました。大幸薬品「正露丸」のラッパのメロディーもそのひとつです
ではなぜ、五感による消費が求められてきているのでしょうか?
まずはネットとスマホ利用による間接体験の肥大や、視覚情報への過度の依存を挙げることができるでしょう。隣席の人と、会話をせずにメールで連絡しあうような仕事環境。電車に乗れば、スマホゲームに夢中になって他人の足を踏んでも気づかない人たち…。多様な身体感覚でのコミュニケーションの復活を、誰しもどこかで望んでいるはずです。CDは売れなくてもライブ人気が根強い背景にも、同様のニーズが潜んでいるのかも知れません。
わが国はいまや、過剰なほどの無菌・衛生社会を形作っているといえます。商品や商業空間においては特に、です。江戸前期の俳諧師・野沢凡兆に「市中はものの匂ひや夏の月」という句がありますが、本来市場とは、物の匂いや感触、売り手のかけ声や身体、熱気といった生命力を感じられる場であったはずです。五感商品たちは、商(あきない)に生命力と色気を取り戻すきっかけとして登場してきたともいえるでしょう。