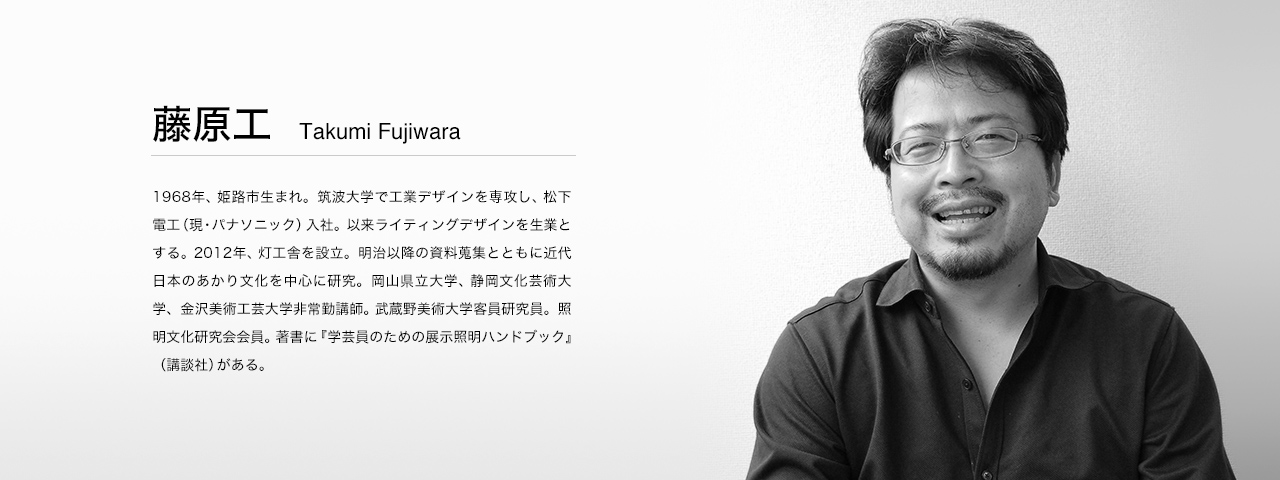日本のあかり文化を、デバイスの歴史から考える
2015.10.29
日本のあかりはどんな歴史を歩んできたのでしょうか。時代劇や浮世絵で目にする行灯や提灯。それら「昔の照明器具」がどのように生まれてきて、どんな使われ方をしてきたのかを知ることは、日本人の美意識や自然観、そして日本そのものを考えることとつながっていきます。美術館博物館の照明デザインの第一人者である藤原工氏に、特に江戸期を中心にして日本のあかり文化の変容について話を聞きました。
【本稿は、国際基督教大学博物館湯浅八郎記念館で開催されている展覧会「昔のあかり」(~11月13日)に際して行われた公開講座「あかりからLEDへ 人をとりまくひかりの変遷」を、編集部の文責により抜粋、再構成したものです】
自然物から灯油へと燃焼の対象が移ることにより、煮炊きをする熱源から、あかりとしての火が独立し、あかりの安定と自由を得ることができました
日本のあかりの歴史は、木などの自然物を燃やすことからはじまりました。次にあかりの燃料としたのは「灯油」です。直接、灯油に火は点きませんので、灯油にひたした灯芯に火をともす方法で広まっていきました。自然物から灯油へと燃焼の対象が移ることにより、煮炊きをする熱源から、あかりとしての火を独立させ、あかりの安定と自由を得ることができました。この流れは世界共通といっていいでしょう。
油を使ったあかりに用いられる器具で代表的なものは「灯台」です。灯台の特徴ですが、「火皿」と呼ばれる器がついていることです。火皿に油を注いで、「灯芯」にひたします。灯芯が油を吸って、油が気化して炎がうまれるのです。灯芯の素材はイグサ科のイ(和名・灯心草)という植物で、その髄を取り出したものを芯として使っていました。
油のあかりは古墳~飛鳥時代には使われたと考えられ、初期の灯台の代表的なものは「結灯台(むすびとうだい)」です。簡易な形で三本の棒をくくってひとつの台としているため、若干不安定なものでした。その後、身分階級の台頭とともに、安定性のました、デザインされたものがでてきました。そのなかのひとつに「牛糞灯台(ぎゅうふんとうだい)」があります。支える台が牛の糞に似ていることから名付けられました。位の高い平安貴族が愛した高級品です。支える台の意匠違いで「菊灯台(きくとうだい)」というものもあります。

【写真①】江戸時代に広まった「行灯」。写真は日本が誇る「有明行灯」です。満月、三日月、半月など月の満ち欠けを行灯の窓に模して、その形状を面にほどこすことによって違う明るさをつくりました。あかりを外にだしてもなかに収めたままでも使える優れものです。陶器は、火皿から落ちる油や灯芯のかすなどから、行灯を汚さないために用いられた「行灯皿」
江戸の庶民のあかり「瓦灯」
灯台の柱は、長いものと短いものがあります。柱の長い灯台は、高い位置であかりをとることができ、主に部屋を明るくするために用いられ、一方、柱の短いものは、主にひとの手元を明るくするために用いられました。その代表が「短檠(たんけい)」です。低い位置であかりがとれるため、茶室などでよく使われています。
長い柱の灯台は屋内のあかりとりとして高い位置にあるので、周囲を照らしだす効率はよくなったのですが、昔の建物は現在のような高機密住宅ではなかったので、すきま風などで消えたりします。その対策として風よけ=風防が必要になってきました。その風防のかたちのひとつとしてでてきたのが、反射板つきの灯台です。この板にはひかりを反射させる役割とと風防の役割のふたつがあります。代表的なものに、法隆寺宝物の「眠り灯台」があります。
わたしたちがいま想像する行灯は、時代劇にでてくるような据え置き型のものです。しかし漢字=「行く灯」と読み取れるように、本来は持ち運ぶために作られた器機でした
室町時代後期には「瓦灯(かとう、がとう)」という器具があらわれます【写真トップ】。灯台のあかりの中でも、江戸の庶民のあかりと呼ばれるものなのですが、いわゆる瓦の土で焼かれていて、瓦職人が作っていたので、この呼び名になったのです。器具のなかでともすと、就寝時のひかりになり、上部に火皿をだすと作業のときのあかりとしても使え、重宝されました。あかりの高さや強さを調整できることも見逃せません。(話し忘れたのですが、不燃素材なので火事を防ぐという側面もあります)
「行灯」の登場
しかしながら、眠り灯台にせよ、瓦灯にせよ、風防のレベルがまだまだ低いことが問題でした。そこで登場したのが「行灯(あんどん)」です。わたしたちがいま想像するのは、時代劇にでてくるような据え置き型のものです。しかし漢字=「行く灯」と読み取れるように、本来は持ち運ぶために作られた器機です。実際、初期の頃は、灯台を布やなにかでくるんで持ち歩いていたのです。室町時代の簡易なつくりの行灯に「提行灯」があります。江戸時代には高さが80センチ近くにもなり、しかも結構重たい。それを持ち運ぶのは大変なことだったのは想像に難くありません。

【写真②】使う場所や目的に沿って、様々な行灯がつくられました。左上部は「八間(はちけん)と呼ばれるもので、天井近くから部屋全体を照らしました。台には「提げ灯(さげあかり)」、壁にはブラケットタイプの「掛行灯」が展示されています。展覧会では、照明器具を描いた浮世絵も掲示されているので、当時のひととあかりの関係を知ることができます
行灯も初期のうちはかなりコンパクトなつくりでした。和紙でくるんだだけのものが中心です。移動もできるし、置きあかりとしても使えました。しかし持ち運べたとしても、油を燃やすあかりなので、油がこぼれてしまうとか、定期的に補充しないといけないなど、使うひとの行動範囲が限られてしまうのが問題でした。そこで移動用には油にかわりろうそくを用いるようになりました。行灯は定置型に限定されていくようになります。
では、灯台のあかりと行灯のあかりとではどちらのほうが明るいのでしょう? 実は古くからある灯台のほうが明るいのです。もちろん「灯台下暗し」なので、台の下部は暗いのですが、周囲を明るく照らすことができます。一方、行灯はそこで用いられている和紙の存在、つまり透過率の問題で灯台より暗くなってしまうのです。
ただし、灯台によって周囲が明るくなるためには、前提条件が必要です。周囲に反射率の高い白っぽい素材がないといけないのです。白い素材があれば、灯台のあかりは周辺を明るくすることに寄与できるのですが、日本の昔の室内は白くないので、その条件にそぐわなかったのです。
行灯ではあかりの使い分けができました。たとえば手元で本を読むという場合は、片側の扉を開けて直接の光で読む。柔らかな間接の光と直接的な光を使いわけられるのです
それにたいして和紙で作られた行灯は、和紙の部分がすべて発光面になるので、見た目が明るくなるのです。その時代、和紙は最も反射率が高い素材のひとつでした。行灯のなかでひかりが内部反射すると、結構明るくなったのです。つまり光の能力でいえば、昔の家屋では行灯のほうが明るく感じる効果が高かったというわけです【写真②】。
行灯ではあかりの使い分けができました。行灯は扉がありますので、たとえば手元で本を読むという場合は、片側の扉を開けて読めばいい。直接の光です。柔らかな間接の光と直接的な光を使いわけられるのです。
日本が誇る行灯は「有明行灯」です【写真①】。これは瓦灯に近い機能性を持っています。あかりを、外にだしてもなかに収めたままでも使える優れたものでした。下の箱に収めた場合は、月の形をした小さな窓からもれるあかりを夜明けまでともしました。満月、三日月、半月など月の満ち欠けを、行灯の窓に模して、その形状を面にほどこすことによって違う明るさをつくったのです。
ろうそくのあかりと「提灯」の発明
油を燃料としたあかりは安定性に欠けるうえに、取り扱いが面倒なものでした。もうひとつのあかりといえば「和ろうそく」です。ろうそくは奈良時代に日本に伝来しました。初期は主に宗教的な用途で使われていました。しかし和ろうそくは油のあかりよりも高価で、長らくの間、一部の人々しか使えませんでした。

【写真③】旅の携帯あかりを展示したコーナー。江戸時代に考案された「小田原提灯」のほか、旅行灯や折りたたみ式の「懐中燭台」などが知られています

【写真④】燭台にのせたろうそくを和紙や布でおおった灯火具、「ぼんぼり」。四角形、六角形、八角形、丸形のほか、からくりのようなものまでありました。左は、手で持ち運ぶための「ぼんぼり手燭」です
江戸時代にはいり、産業が発達することにより、和ろうそくの価格も下がりはじめ、普及も進みました。そして、ろうそくを立てる台である「燭台」や提灯などのろうそく用の灯火具が発達します。これら、ろうそくのあかりによって、日本のあかりは更に深化をしていくことになります。
燭台にのせたろうそくを和紙や布でおおった灯火具を「ぼんぼり」と呼びます【写真④】。和ろうそくの炎は無風でも揺れる不安定さがあり、おおいは風よけとしても役立ちました。
「行灯よりも持ち運びがしやすい」「ろうそくは油のようにこぼれるわけではない」ーーぼんぼりはいくつもの特性により、ひとびとに受け入れられていきます。その過程で様々な形状がうまれています。四角形、六角形、八角形、丸形のほか、からくりのようなものまでありました。日本独自の燭台です。そういう意匠に凝るあたりに、日本人の気質が垣間見えるのではないでしょうか。
「これぞ日本!」。それが提灯です。行灯は巨大なため、持ち運びが困難でした。それを解決したのが提灯です。特に軽くてたためる「ぶら提灯」は画期的で、江戸時代に普及しました。提灯は竹ひごと和紙という、手にはいりやすい素材でできていて、何よりも軽い。「折り畳める」点が灯火具の進化としてあげられるでしょう。最初につくられたといわれる折りたたみ式提灯は「箱提灯」で安土桃山時代に現われます。その後何種類もの提灯がうまれますが、その便利さにより行灯にとってかわる存在となります【写真③】。
日本のあかりの原型は江戸時代に完成していた
「江戸時代のあかりは寂しかったのでしょう」といわれることがありますが、そんなことは決してありません。逆に日本のあかりは、江戸時代に日本のあかりのひとつの完成形を迎えるのです。室内だけでなく屋外でも行灯や提灯など、様々なあかりが使われていました。都市部の住居や施設はすでに、照明空間としてじゅうぶんに成立していたのです。

【写真⑤】懐中電灯の元祖ともいえる「龕灯(がんどう)」。江戸時代につくられた桶型の携帯用灯火具です。浮世絵をよく見ると、龕灯によって“黒い怪物”(?)が照らし出されています
人が集まる、大きくて広い空間を照らす照明も江戸時代にはありました。「八間行灯(はちけんあんどん)」です【写真②】。和紙が貼つけられた上部を反射笠にすることで、光を拡散させる仕組みです。拡散光は日本のあかり文化の特徴といえるでしょう。
一昔前には、昭和の頃の日本の風景を指して、「日本は蛍光灯ばかりでブラケット(壁につける照明器具)がない」といった日本のあかり批判がありました。しかし、江戸時代にすでにブラケット型のあかりはいくつもの種類があったのです。
店先や廊下などにかける「掛行灯」はブラケット型の最たる例といえるでしょう【写真②】。スタンド型には燭台やぼんぼりをあげることができます。天井のあかり、壁のあかり、床のあかりーー基本的な室内のあかりは江戸時代には、すべて揃っていたのです。すでにこの時代、ひとびとはそれらをきちんと組み合わせて使っていました。
日本のあかり文化を振り返ると、日本のあかりはすでに二回滅びています。そして現代は三度目の終焉を迎えつつあるといってもいいでしょう。
一度目は明治維新。このとき江戸時代のあかりは、文明開化、つまり西洋のあかりの導入とともに葬られました【写真⑥】。しかしその後、西洋化されたあかりが、日本の独特の感性や技術をとりいれることで日本のあかりとして再構築されることになります。

【写真⑥】幕末に外国から日本に伝わった石油ランプ。明治時代の文明開化を象徴するあかりです
二度目は第二次世界大戦の敗戦。戦時中の金属の供出によって器具がなくなることで、日本のあかり空間が失われてしまいます。しかしその後、昭和30年代の高度成長の時代には蛍光灯を中心とした日本独特の照明世界が培われていきます。再び日本オリジナルのあかり文化が形成されます。
そして三度目の終焉が、いま私たちが暮らす現代です。新しい光源であるLEDやOLED(有機EL)などが再び、あかりの再構築を促そうとしています。新しい光源が登場したというだけなら「終焉」だとはいえませんが、地球温暖化、RoHS、311、水俣条約などが相まって、これまで普通に使っていた電球、蛍光灯などがこの先10年ほどでなくなり、それがすべてLED、OLEDに代わってしまうのです。そこであかりの再構築がおこなわれないわけはありません。
日本のあかりは今後、激動の時代を迎えるはずです。西洋ランプが幕末に外国から伝わったのが1860年代。それからたかだか150年の間に、日本のあかり文化は驚くべき変容を経験してきました。さらにこれから10年、20年でまったく新しいひかりの文化が創出されることになるでしょう。日本人の感性にあった、日本のあかり文化がうみだされることが望まれます。
(写真提供/国際基督教大学湯浅八郎記念館 撮影/斎木 修)

■展覧会「昔のあかり(JAPANESE LIGHTING DEVICES)」
会場:国際基督教大学博物館湯浅八郎記念館
住所:東京都三鷹市大沢3-10-2
会期:開催中 〜11月13日(金)
10:00-17:00(土曜日は16:30まで)日月祝休館
入場無料
http://subsite.icu.ac.jp/yuasa_museum/