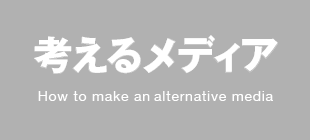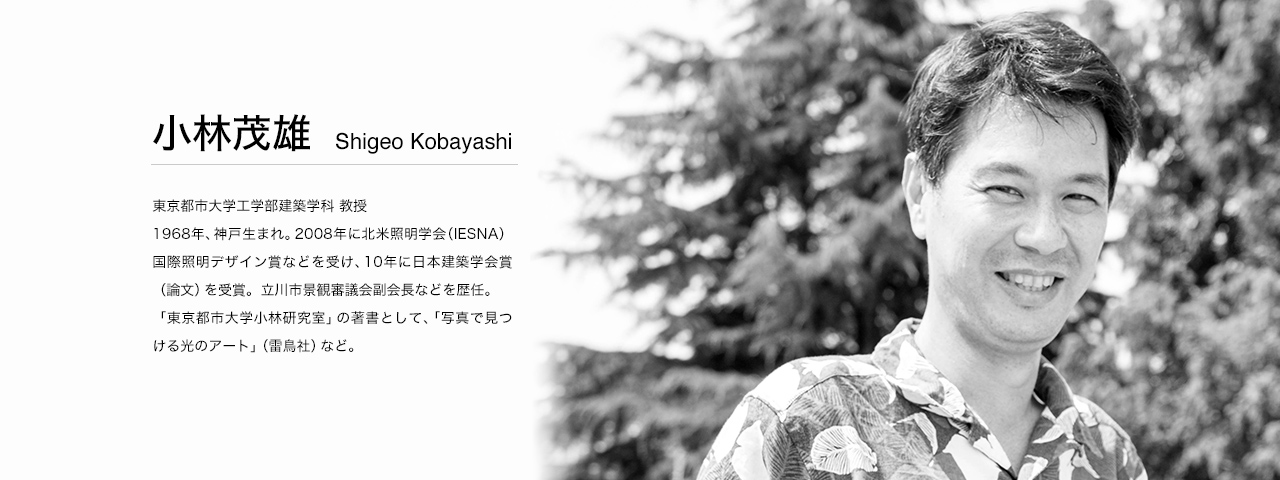歓楽街のネオンはなぜ赤い?「禁止された向こう側」への誘い―光と経済活動
2015.08.18
警告をあらわす赤、興奮を呼び攻撃性を高める赤、食欲を喚起する赤、夜の街で怪しく誘う赤。赤い光が人に及ぼす心理的な効果とは。
世界共通で「危険」「停止」を表す赤色光
事故や災害など緊急事態が発生したとき、速やかに救護や防火活動ができるように「色」が用いられる。色を見れば文字を読まなくても人は直感的に判断し、何を意味しているか素早く理解できるためだ。
何の色を何の警告や指示に用いるかということは、JIS(日本工業規格)の安全色(JIS Z 9103:2005)によって決められている。「赤」は防火、禁止、停止、「黄」は注意、「緑」は安全、避難、進行など。すなわち信号機に用いられている色である。これらの安全色は、以前は各国で統一した規格はなかったのだが、近年は全世界で共通させようとしていて、国内ではISO(国際標準化機構)に合わせる形で2005年に改定された。
最も緊急を要する警告には「赤」が用いられる。青や緑が他の色に比べて目立ちにくいのに対して、赤は誘目性(目立ちやすさ・発見のされやすさ)が高く1)2)、識別性(複数の対象の中での区別・認識のしやすさ)が高い色である。消火器や一時停止の標識に赤が塗られているのはこうした理由だ。

そして赤く発光する光についても、防火、禁止、停止といった緊急性の高い警告を知らせる目的で使われる。危険を示す道路工事中のランプや発炎筒、ビルの上にある航空障害灯、火災報知機を示すランプ、緊急時に押す停止ボタン、救急車やパトカーの警告灯。赤く発光すればするほど、その警告を知らせる効果は強くなる。
もともと目立つ赤だが、こうした規格によって、私たちは日常的に「緊急事態である」「目にしなければいけない」という意識が刷り込まれていることになる。
興奮を呼び起こし攻撃性を高める赤。赤いユニフォームを着ている選手は青いユニフォームより勝ちやすい?
バーゲンやワゴンセールの広告や値札に使われる赤色。ここでも、赤が「非常時」「危機」を示すことが利用されている。赤い大きなサインには無意識に注意が向くように仕組まれているというわけだ。
さらに、赤は緊急時であることを知らせるだけではなく、人を興奮状態に導き、攻撃性を高めたり購買欲を高めたりする効果があると言われている。例えば、スポーツ選手のユニフォームは赤が多く用いられる。2004年のアテネ・オリンピックの競技を分析したイギリスの研究者らは、赤いウエアを着用した選手は青いウエアを着用した選手に対して、55%、つまり半数よりも5%も多くの試合で勝利していることを示した3)。
ただし一方で、スポーツの種類や選手によっては、赤色のウエアを着ても試合結果には影響しなかったという報告もある4)5)。また、赤い光の中で過ごす人の心拍数や脳波など生理機能を調査した別の研究では、他の光色と有意な差はなかったという6)。どうやら赤い光や赤い服が、誰に対しても常に攻撃性を高めたり興奮させたりするわけではないようで、それ以上詳しいことは今のところ分かっていない。状況によってそういう効果があることもあると考えればいいだろう。
購買行動に関しては、バージニア工科大学の研究者らが、ネットオークションサイトにおける画面背景の色と入札額との関係を調べている7)。その結果、赤色のバナーを見せられた被験者は、高い入札額を提示する傾向を示した。赤が誘発する攻撃性は、購買意欲にも影響を及ぼし、売り場に示された赤いキャッチコピーや装飾は、(他の人よりも早く)購入したいという衝動を高めるのだ。
禁止された向こう側への誘い―歓楽街のネオンはなぜ赤いのか
歓楽街のパチンコなどのネオン。実は、ネオンが赤いのはその出現時までさかのぼる。ネオン管のルーツは、1910年にパリで公表された低圧放電灯の一種で、封入するガスによって発光する色が異なるが、ネオンガスが封入されたネオン管は赤色に発光した。その後、アルゴンやヘリウムの封入によって多様な色を発光できるようになったものの、当初のネオンガスの赤色光が今でも最もよく使われている。
赤いネオンがラスヴェガスなどのカジノで多く使われるのは、赤が攻撃性を助長し、「儲けたい」という欲望を刺激するからだろう。光を赤くすると下品になりやすいので、カーペットを赤くする場合も多い。劇場のネオンや赤い内装は非現実的な世界を演出する。長波長の赤色は、明るい空間から暗い空間へ移った時に起こる視力の暗順応を早くするという利点もある。

赤色は攻撃性のほか、女性の性的魅力を高めるとも言われている。フランスの研究では、ウエイトレスが赤い服を着ていると、男性客はチップを14~26%多く払ったという8)。この報告によると、チップを多く払ったのは男性客だけで、女性客には全く効果がなかった。つまり、赤い服が異性に対する魅力を向上させたというわけだ。
この効果を知ってか知らずか、アムステルダムの夜の歓楽街には、軒に決まって赤いランプが灯されている。「レッド・ライト・ディストリクト」と呼ばれる一画だ。赤い光は、日常的には「禁止」された向こう側へ誘うことを暗示する。そして、赤い光で照らされた女性は血色がよく見え、性的魅力が強調される。さらに、レッド・ライト・ディストリクトで赤くなるのは、女性ばかりではない。窓明かりも赤やピンクをまとい、この光によって、内部の秘め事を街にさらけ出し、誘っているように感じられる。
赤い光と青い光。男女で違う食欲に及ぼす効果
赤色が刺激するのは性的な欲求ばかりではない。赤、オレンジ、黄など暖色系の色彩は食欲を刺激することが国内外の研究で知られている9)10)。実際に、レストランの内装や看板にはこうした色が多用され、テーブルも色温度の低い電球色の照明が使われるのが一般的だ。また赤提灯の光は、人を刺激し誘引すると同時に、食欲への刺激と、安く大衆的な店であるということを暗示する。
飲食空間では、料理が最も美味しそうに見える照明を追求するもので、それはあまり極端な色付きの明かりでないほうがよいと言える。しかし筆者の研究室では、研究の一環として、様々な食品の食欲が色付きの照明によってどの程度低下するか、実験を行ったことがある11)。そしてその結果、青色光や緑色光に比べて、赤色光で照らされた食品に対する食欲は低下しにくいこと。そして男性よりも女性の方が、青や緑の寒色系の光で食欲が低下しやすいことが分かった。
やや強引だが、これらの結果を応用するなら、例えば男性の理性を狂わせたい空間で、温かい食事を提供する場合は、赤色光で照明することが効果的だ。そして、個性的な空間にしたいと思っていても、お客に冷静さを保ってもらいたい場合、そんな空間でデザートや飲み物を提供しようとする時は、青色光や緑色光で鮮やかに照明することが効果的だといえるだろう。
参考文献
- 神作博、福本 純一:安全色彩の誘目性について、日本色彩学会誌 1(1), 4-14, 1972-10
- 落合 信寿 , 佐藤 昌子:安全色の探索に及ぼす周辺刺激の色と配置の影響、デザイン学研究 49(4), 85-94, 2002-11
- Hill, Russell A., and Robert A. Barton (2005), “Red Enhances Human Performance in Contests,” Nature, 435, 293.
- Pollet, T. V., & Peperkoorn, L.S. (2013). Fading Red? No Evidence That Color of Trunks Influences Outcomes in the Ultimate Fighting Championship (UFC). Frontiers in Psychology, 4(643). doi: 10.3389/fpsvg.2013.00643
- 岩瀬 雅紀、高井 茂、杉山 喜一:ボールゲームにおけるユニフォームの色彩効果(2) : 大学バスケットボール部員によるバスケットボールゲームから、日本色彩学会誌 24(1), 11-17, 2000-03-01
- Caldwell, J. A., & Jones, G. E. (1985). The effect of exposure to red and blue light on physiological indices and time estimation. Perception, 14, 19–29.
- Rajesh Bagchi and Amar Cheema. “The Effect of Red Background Color on Willingness-to-Pay: The Moderating Role of Selling Mechanism.” Journal of Consumer Research: February 2013.
- N. Gueguen, C. Jacob.: Clothing Color and Tipping: Gentlemen Patrons Give More Tips to Waitresses With Red Clothes. Journal of Hospitality & Tourism Research, 2012
- Birren, F.(1963). Color and human appetite. Food Technology, 17, 553-555
川染 節江:食品の色彩嗜好に関する年齢および男女間の変動、日本家政学会誌 38(1), 23-31, 1987 - 小林茂雄:鮮やかな光色で照明された食品に対する食欲、日本建築学会環境系論文集、Vol.74、No.637、pp.1341-1346、2009.3